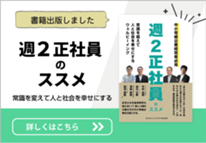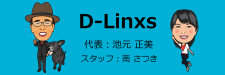【キャリア開発・組織開発支援】≪九州≫ 人材育成/企業研修/セミナー/キャリアコンサルティング

個人向けにはカウンセリング、能力開発という側面で支援。
組織向けでは人材育成、組織開発の視点から潜在している課題を明確にし、解決の糸口を探っていきます。
《感想》「鹿児島の歴史に学ぶ持続可能な社会づくり 」共創の場づくり(2021年9月18日感想)
令和3年度指宿市共創の場月理事業
「鹿児島の歴史に学ぶ持続可能な社会づくり」
2021年9月18日(土)14:00~16:00に
指宿市ふれあいプラザなのはな館 視聴覚室で開催しました。
*SDGsの概要
*薩摩藩の得意な社会
・薩摩藩が抱えていた財政の状況と財政改革の必要性
・品質管理の向上の必要性
・増産及び収益増のための肥料の重要性
・指宿の海運商、黒岩藤右衛門からの「鯨骨、牛馬骨が薩摩の土地柄に向いている」との情報をきっかけに、薩摩藩内に設けた公設の骨粉肥料供給施設「山健会所」の設置。
・骨粉を生産するための水車
*菜種子の製造・輸送と山川の港と水車
・菜種子および菜種油の製造・輸送拠点としての条件が第一に整っていた山川港
→ 当時の国図絵に記入された薩摩藩の港に関する情報や江戸の講釈師伊藤凌舎が残した「かこしまふり」、オランダ海軍将校・カッテンディーケの記録などにも記載されており、水車は技術的にも最新の技術を持っていたようです。
*天保年間に、南薩地域で展開した菜種子栽培は、様々な分野と関わりながら薩摩と大阪、そして日本各地へと物流の循環と富の配分を行っていた。
→ ある意味では、藩の利益と領民の利益を実現する「国益」のモデルが目指されていた。
<以上、当日の資料より>
*天保の改革の際に重要な拠点となった山川港の特徴
*古文書に書かれた指宿の持ち味
*海運を中心とした物流拠点としての山川の存在価値
*薩摩藩の財政改革と事業家たちの活動
*様々な情報や技術の融合から発展した独自の循環型社会
などなど、様々な視点で知識を得ることが出来ました。
ありがとうございました。
![]() とても分かりやすい話をしていただいたので、大満足でした。「歴史」×「SDGs」という視点で学んだことは、初めてだったが素直に入ってきた。すごく新鮮な気持ちになった。
とても分かりやすい話をしていただいたので、大満足でした。「歴史」×「SDGs」という視点で学んだことは、初めてだったが素直に入ってきた。すごく新鮮な気持ちになった。
![]() SDGsは学ぶ機会があり、少しは知っていましたが、歴史との結び付けて新しい感覚でした。薩摩藩と言えば、島津、西郷、小松、調所さんの名前は知っていましたが、指宿出身の黒岩さんは新しい知識でした。我が家のお隣さんが黒岩さんなので楽しく講話を聴くことができました。山川港が菜種油の輸送の拠点だったことを知りビックリしました。また聞きたいです。
SDGsは学ぶ機会があり、少しは知っていましたが、歴史との結び付けて新しい感覚でした。薩摩藩と言えば、島津、西郷、小松、調所さんの名前は知っていましたが、指宿出身の黒岩さんは新しい知識でした。我が家のお隣さんが黒岩さんなので楽しく講話を聴くことができました。山川港が菜種油の輸送の拠点だったことを知りビックリしました。また聞きたいです。
![]() 200年前の循環社会が、時代が廻り注目されるのは興味深かったです。鹿児島の特性で牛馬骨に抵抗が少なかったり、海外の知恵を利用する力を持っている先人の地であることを再認識しました。
200年前の循環社会が、時代が廻り注目されるのは興味深かったです。鹿児島の特性で牛馬骨に抵抗が少なかったり、海外の知恵を利用する力を持っている先人の地であることを再認識しました。
![]() 地域の産物を、水車を活用して、生産性を持たせていく、そういう循環が凄いなと思った。成川浜の滝は成川―鳴川―滝―爆音からきている。菜種油を作っていたことから、火薬工場になったということだった。山川が県下でも優れている港だということが、驚きでもあり、自信にもなった。
地域の産物を、水車を活用して、生産性を持たせていく、そういう循環が凄いなと思った。成川浜の滝は成川―鳴川―滝―爆音からきている。菜種油を作っていたことから、火薬工場になったということだった。山川が県下でも優れている港だということが、驚きでもあり、自信にもなった。
![]() 資料から当時の見識力としてかなり機能していたと思われるが、現代の動きとしての判断力が期待されます。
資料から当時の見識力としてかなり機能していたと思われるが、現代の動きとしての判断力が期待されます。
![]() 先祖が武士であったとのことを父に聞いていました。3,4人に1人の割合であったとのこと、本当だったのですね。山川の港が薩摩に役立ったことを初めて知りました。今は何かその頃の名残は無いのですか?持続可能な社会を作れたらいいですね。
先祖が武士であったとのことを父に聞いていました。3,4人に1人の割合であったとのこと、本当だったのですね。山川の港が薩摩に役立ったことを初めて知りました。今は何かその頃の名残は無いのですか?持続可能な社会を作れたらいいですね。
![]() 知らなかった地元指宿の歴史を知ることが出来、勉強になりました。昔からの知恵や歴史から学びつつ、今私たちができるやり方で持続可能な社会づくりをしていけたらいいなと思いました。
知らなかった地元指宿の歴史を知ることが出来、勉強になりました。昔からの知恵や歴史から学びつつ、今私たちができるやり方で持続可能な社会づくりをしていけたらいいなと思いました。
![]() 分かりやすい講座でした。ありがとうございます。昔は今に比べ情報収集が大変だったと思います。いかに行動力、技術力等すばらしい力を持った人が多かったことか――――― 持続可能な社会づくりのためには市民一人ひとりができることを力を出し合い、協力していくことが大切だと思います。
分かりやすい講座でした。ありがとうございます。昔は今に比べ情報収集が大変だったと思います。いかに行動力、技術力等すばらしい力を持った人が多かったことか――――― 持続可能な社会づくりのためには市民一人ひとりができることを力を出し合い、協力していくことが大切だと思います。
![]() 昔の話だが、いろいろな壁を乗り越えて循環型社会を作り上げたことを学び、すごく面白かった。
昔の話だが、いろいろな壁を乗り越えて循環型社会を作り上げたことを学び、すごく面白かった。
(順不同ですべての感想を載せさせていただいています)
ご参加&ご感想、ありがとうございました。
です。
(ディーリンクス 代表 池元正美)